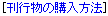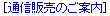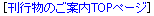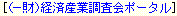今般、産業構造審議会通商政策部会不公正貿易政策・措置調査小委員会から、「2007年版 不公正貿易報告書」が公表されました。1992年の第1回報告書から数えて、今年で16回目の公表となります。
本報告書は刊行以来、各国の貿易政策・措置が不公正か否かは国際ルールに基づいて判断すべきであるという「ルール重視の視座」を維持して来ました。このような我が国の姿勢は、経済力等の差を背景とした通商紛争の一方的解決を阻止し、ルールに基づいた第三者の公平な判断によって紛争を解決するWTO紛争解決メカニズムの定着とともに、広く国際的にも評価・共有される価値観となりました。また、第三者の公正な法的判断の蓄積により、WTO協定の解釈が明確化されることは、グローバルに展開する産業界にとっての予見可能性を担保することにも繋がります。
重要なことは、ルールに基づいて具体的問題を1つ1つ解決することです。このため、2004年以降、「経済産業省の取組方針」を策定し、優先案件をリスト化するとともに、右取組方針に従って、WTO手続・二国間協議等を通じた問題解決を図って参りました。このような努力を通じて多くの問題が解決されて来ましたが、本報告書に記載されているとおり、各国の貿易政策・措置の中には、WTO協定等国際ルールに照らし問題があると思われる措置が、いまだに存在することもまた事実です。こうした措置に対して是正を求めることは、我が国への不利益を除去するのみならず、協定の実効性を担保するためにも重要であり、今後ともWTOや二国間協議等の様々な機会を通して、積極的に改善を求めていきたいと考えています。
また、本報告書が刊行された1990年代以降、世界の多くの国・地域で二国間・地域間の協定が締結されるようになり、我が国も2002年以降、シンガポール、メキシコ、マレーシア、フィリピン、チリ、タイとの間で経済連携協定(EPA)を締結しました。その結果、貿易政策に係る我が国の権利・義務を規定する国際ルールにおいて、経済連携協定・投資協定といった二国間協定の占める割合が増しています。特にWTO協定において十分な規律が設けられていない投資等の分野では、経済連携協定等が独自の紛争解決制度を伴った秩序を構築しており、国際的には、近年、その活用を通じた紛争解決事例が急増しています。これらの規律が、WTO協定を補完する新たな国際ルールとして遵守されていくことは、「ルール重視の視座」にも適うものです。
こうした観点から、本年の報告書では、WTO協定のみならず、二国間・地域間の協定についても、今後の紛争解決のベースとなる法的枠組として積極的に位置づけ、初めて体系的な解説を行っています。これまでWTO協定及び経済連携協定等を体系的に学ぼうとされていた企業実務に携わる方、研究者、学生ほかの皆様にとって、本報告書がその一助となることを期待しています。また、本報告書を通じてWTO協定及び経済連携協定等の国際ルールに対する理解が深まり、これを背景に不公正な貿易政策・措置に対して官民が連携し改善を求めることにより、我が国企業ひいては貿易大国である我が国にとっての国益の維持・増進が実現されることを願っています。
最後に、本報告書の執筆にご尽力いただいた委員の皆様方に対し、心から敬意を表しまして、刊行にあたっての挨拶とさせていただきます。
2007年4月


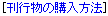

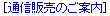

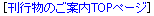

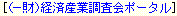
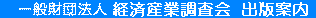


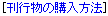

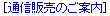

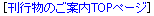

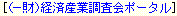
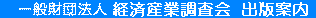
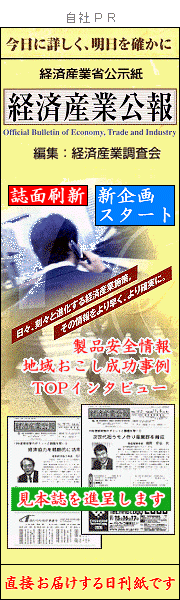
![]()