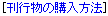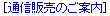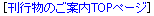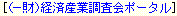梁煕艶君は、2003年4月に大阪大学大学院法学研究科修士課程に入学し、2005年4月に同研究科博士課程に進み、2008年3月に法学博士号を取得した。本書は、その博士論文「中国における特許保護の現状と課題―日本法との比較法的研究―」に、その後の中国特許法の動向等を追加したものであり、本書の出版に当たり、大学院での指導教員として、梁君及び本書を紹介させていただく。
梁君は、日中特許法の比較を研究テーマとして、大学院に入学したが、入学時には既に、日本の弁理士に相当する中国専利代理人の資格を有しており、中国特許法に関して広い知識を備えていた。また、三協国際特許事務所において特許関係の実務に携わっていたことから、日本特許法も相当に理解していた。大学院の修士課程及び博士課程においては、日中特許法の知識理解を一層深めつつ、両法の比較法的研究を行った。
梁君は、日本語の読解能力にも優れ、多くの日本語文献を正確に読みこなし、また、日本語を話したり聞いたりすることにも特に問題はなかった。大学院での研究は、ほぼ定期的に、研究の成果としてある程度まとまったものを作成し、それを私と一緒に議論して完成させていくという方法で進めていた。もっとも、私がコメントすることはあまり多くはなく、指導教員である私にとっては、正直なところ、大変楽な院生であった。
さて、本書は、中国特許法を日本特許法と比較検討し、その結果を踏まえて、中国の国情に適した制度改正を提言するものである。中国は巨大な市場であり、我が国にとって重要な貿易相手国であることから、中国特許法への関心は高い。もっとも、中国特許法の条文を見るだけでは、その実像を知ることは難しいが、この点、本書では、多くの中国の裁判例や学説に基づいて、中国の特許制度の現実の姿が明らかとされている。主として論じられている問題領域も、「特許権の効力及びその効力が及ばない範囲」(第一章)、「特許権の保護範囲の認定」(第二章)、「特許権侵害の抗弁事由」(第三章)と、いずれも重要なものである。中国特許法は、日本法・アメリカ法・ヨーロッパ法を参考にして策定されたものであり、それ自体、研究対象として興味深い点が多々ある。そのため、日本法との比較研究を行う本書は、上述の実務的な関心に応えるだけでなく、我が国での特許法の研究に貢献するところも少なくないと思われる。
中国特許法の現状を詳細に示し、その問題点を指摘し、今後の方向性を論じる本書は、実務的な面からも、また学問的な面からも高く評価されるものと信じる。
大阪大学大学院高等司法研究科
大阪大学大学院法学研究科
教授 茶園成樹
2008年10月吉日


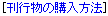

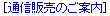

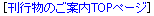

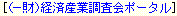
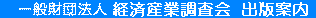


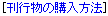

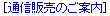

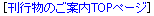

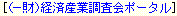
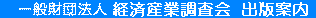
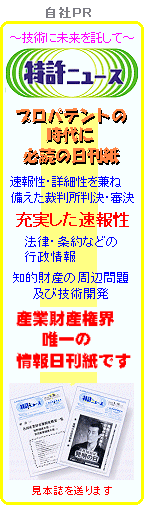

![]()