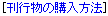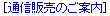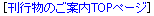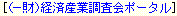日本経済は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大を続けています。日本の競争力の象徴である自動車産業やその関連企業が立地する地域では、既に深刻な人手不足となっているほどです。一方、農業、建設業などが中心の市町村は、景気回復から大きく取り残されています。また、中小企業の経営者からは、景気回復が実感できないという声が多く寄せられています。
これまでの好況期との違いは、日本全体が良くなったのではなく、業種、企業規模、地域による格差が大きいことです。日本の競争力を支えているのは中小企業です。地域が繁栄する経済とならなければ景気回復の意味はありません。今後も安定的な成長を持続するためには、地域や中小企業に元気になってもらう必要があります。
このような観点から、経済産業省が中心となってとりまとめを行い、昨年の7月に政府・与党で決定された「経済成長戦略大綱」では、地域・中小企業の活性化を、大きな柱の一つとして取り上げています。経済産業省としては、この大綱に掲げられた施策を着実に実行し、これを、地域・中小企業の活性化に結びつけていくため、平成19年の通常国会に、大綱関連の3つの法律案を提出しました。そして、三法案とも全会一致あるいは賛成多数で成立しました。本書では、その具体的な内容と背景にある基本的な考え方について詳しく説明したいと思います。
第1章では、なぜ、今回の景気回復が、個人や地域・中小企業から見て実感がないと言われるのか、その原因について、分析します。そして、特に、地域が景気回復を実感出来るようになるためには、地域の産業構造自身を変えていく必要があると言うことを示します。
第2章では、新経済成長戦略を実現するために、これまで、経済産業省が中心となって取り組んできた予算、税制改正などの状況についてご説明します。
第3章では、イノベーションを促進し、サービス産業の生産性向上に向けた企業の取組を支援する「産業活力再生特別措置法」などの改正について解説します。
また、第4章では、地域に企業立地を促進するための5つのポイントを説明し、そのための「地域産業活性化法」について解説します。
最後に、第5章では、地域が独自の地域資源を核として、新たに産業を興していこうとする取組についてご紹介し、そのような地域の努力を支援するための「中小企業地域資源活用促進法」について解説します。
経済産業省としては、今後とも、経済成長戦略の具体化に向け、省を上げて取り組んでいく決意です。
本書は、大綱関連3法を担当した経済産業省の担当課長自身が執筆に当たり、地域・中小企業を活性化していくために何をしなければならないかについて、できるだけわかりやすく説明するように努めたつもりです。本書が、地域経済の、そして日本経済の将来に関心がある皆さま方のお役に立てればと考えています。
最後になりましたが、経済成長戦略大綱の実行と法案の成立に向けた業務に夜を徹して精励してくれた同僚たち、そして、ご協力いただいた数多くの外部の方々に心から感謝を申し上げます。


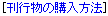

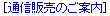

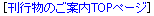

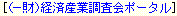
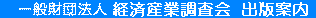


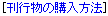

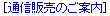

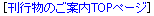

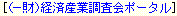
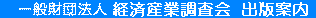
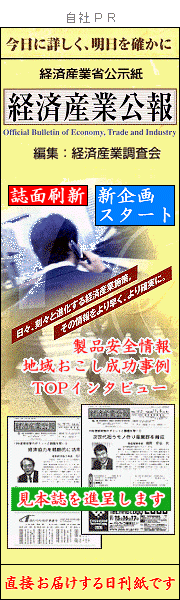
![]()